各種勲章の買取実績
掲載されている買取実績についてご質問などありましたら、下記までお問い合わせください。
TEL . 0120-766-299
MAIL . contact@romandrop.jp
営業時間. 9:00 ~ 18:00
ご家族が亡くなり、いざ遺品整理をしようとしても、価値が判らない、物が多すぎてどこから手をつけて良いのか判らないなど、頭を悩ますことが多いですよね。
生前大事にされていた形見の品など、無暗に手を付けるのは故人に対し申し訳ないと、処分するにもなかなか手が進まない場合もあるでしょう。
浪漫ドロップではそんな悩みの多い遺品整理を、遺品整理士の資格を持った担当者がご遺品の買取をさせて頂いています。
故人が大切にしていたコレクションや、お家の家財道具一式は勿論のこと、引き継いだ物の量が多すぎて置き場所に困っているご遺品の数々を、適切に選別させて頂き高価買取いたします。
遺品整理にて売りたい骨董品や美術品、故人が大切にしていたお品物がありましたら、浪漫ドロップへお任せください。

ご空き家やリフォーム・建て替えで古くなったお家や蔵の解体をする際、処分に困るのが解体業界で「残地物」と呼ばれる廃棄物です。
解体業者さんに処分を依頼すると追加料金がかかるので、解体費用より処理費用の方にお金がかかってしまったり、本来は売れる物でも処分費用がかかってしまったり、お客様が損してしまうケースが多いです。
そんな悩みの種の「残地物」を浪漫ドロップでは丁寧に選別・査定させて頂き価値を見出し高価買取しております。
旧家・古民家、蔵の残地物でお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
美術品や骨董品の買取は勿論のこと、格子戸や帯戸、藏戸などの建具類まで、家屋や蔵の中のお品物を無料査定・出張買取致します。
家屋や蔵を解体するご予定がありましたら、何も処分しない状態で取り壊す前にぜひ、浪漫ドロップへご連絡下さいませ。

勲章(くんしょう)を知る
秩序維持に有用な褒賞制度
勲章とは、大きな功績や優れた業績を成した個人を表彰する国家制度のひとつで、正装等に着用する装飾品や賞状等の形で授与されます。11世紀から13世紀頃にヨーロッパで考案された騎士団記章がその起源とされ、日本では幕末(19世紀半ば)に薩摩藩が製作して海外要人へ授与したものが最初で、明治以降政府により本格導入され現在まで存続します。 社会秩序を乱す者には懲罰、その維持発展に寄与した者には褒賞を与える信賞必罰の原理。勲章は社会の維持・発展に不可欠な秩序維持に有用であるこの原理の一方を支える栄典制度の一つとして導入・運用されてきました。中世起源ながら世界の近代国家にも有用とされる勲章。今も多くの国で運用されますが、ここでは日本の勲章について解説します。
勲章の種類
日本では栄典授与の為に位階・勲章・褒章・記章・賜杯等が用意されてきました。その内、勲章・褒章とそれを補完・代替する賜杯や記章が広義的に勲章の範疇に入ります。 現在の日本の勲章には、大勲位菊花章頸飾(だいくんいきくかしょうけいしょく)・大勲位菊花大綬章(だいくんいきくかだいじゅしょう)・桐花大綬章(とうかだいじゅしょう)・旭日章(きょくじつしょう)・瑞宝章(ずいほうしょう)・宝冠章(ほうかんしょう)・文化勲章があり、旭日章と瑞宝章は「大綬章」「重光章(じゅうこうしょう)」「中綬章(ちゅうじゅしょう)」「小綬章(しょうじゅしょう)」「双光章(そうこうしょう)」「単光章(たんこうしょう)」、宝冠章は「大綬章」「牡丹章(ぼたんしょう)」「白蝶章(しろちょうしょう)」「藤花章(とうかしょう)」「杏葉章(きょうようしょう)」「波光章(はこうしょう)」の各6種(等級)に細分されています。この他、戦後廃止された「金鵄勲章(きんしくんしょう)」全7等級や、平成に廃止された旭日章下位の「青色桐葉章(せいしょくとうようしょう)」「白色桐葉章(はくしょくとうようしょう)」と宝冠章・瑞宝章の下位2種もありました。 個人の生涯功績を称える勲章とは異なり、特定の事績毎に授与される褒章には「紅綬褒章(こうじゅほうしょう)」「緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)」「黄綬褒章(おうじゅほうしょう)」「紫綬褒章(しじゅほうしょう)」「藍綬褒章(らんじゅほうしょう)」「紺綬褒章(こんじゅほうしょう)」があり、再度褒賞される場合に賜与される「飾版(しょくばん)」もあります。また賜杯には銀杯と木杯があり、勲章にかえて授与されるものには菊紋、褒章条例に基づき授与されるものには桐紋が入りました。そして記章の内、勲章の範疇に入るものでは、戦前は国家行事や事変協力者に授与される「記念章」や戦役参加者に贈られる「従軍記章」、戦後は自衛隊の「防衛記念章」や「海上保安庁表彰記念章」等があります。
勲章の序列・授与対象
勲章授与の対象者は、戦前では最高位の大勲位が「偉勲ある」皇族や元老等、次位の桐花章とその下位の旭日章が「勲功顕著」な者、その次位の瑞宝章が「勲功及び積年の勲労ある」公職者等、宝冠章が皇族や海外の要人夫人等の女性、文化勲章が「文化の勲績卓抜なる」者、金鵄勲章は「武功抜群なる」軍人軍属となっていました。文化勲章以外は基本的に非民間人を対象としており、旭日章・瑞宝章・宝冠章は勲一等から八等、金鵄勲章は功一級から七級までの等級がありました。戦後は同様の基準を持ちつつも年金・特権が廃止され、のちには等級廃止・簡略化も行なわれて、官民・男女格差の是正も図られました。
勲章の意匠と内訳
勲章の最大の特徴は貴金属等を使用した工芸品的美しさです。特に日本のものは造りや材質が良く、海外でも人気があります。勲章本体の章(しょう)は金銀に色とりどりの七宝(しっぽう)を施したもので、旭日や宝冠等が表現され、その上には紐(ちゅう)と呼ばれる桐花紋の金具、更に上部の環(かん)によって吊り布の綬(じゅ)と接続されました(古くは章と紐の一体型もあり)。綬は大綬章が肩掛け型、中綬章・重光章・文化勲章が首掛け型、小綬章以下は胸部取付用の小片となっており、勲七等・八等相当は紐が章となっており、最高栄誉の大勲位頸飾は綬に代わり精緻な金属製の首飾りが付きました。なお、各勲章の意匠は、その創設時より基本的に同様ですが、若干の変更もあります。 また付属品として、勲一等相当には二等正章(無綬直付け式)の「副章」、二等相当には三等正章の副章に、大勲位頸飾以外には綬と同素材で作られた小円状等の「略綬(りゃくじゅ)」、それらが収まる黒漆塗や黒革・紙革貼の木箱、更に全員に氏名等の記載や精緻な勲章絵柄が施された「勲記(くんき)」が用意され、天皇の名の下に授与されます。そして受章者は、規程に則り勲章と副章を正服等に、略綬を平服等で佩用(はいよう)します。
勲章の歴史(褒章・賜杯・記章等除く)
日本で最初に作られた勲章は、幕末の慶応3(1867)年に薩摩藩が製造したものです。それは「薩摩琉球国」という文字と藩主島津家の家紋である「丸に十」をあしらった十字紋で、フランスのレジオンドヌール勲章を参考としたものでした。それは、当時行なわれたパリ万博にてナポレオン三世を始めとするフランスの要人に贈与され、好評を博します。 明治政府成立後は、外交儀礼上等での勲章の重要性が認識されて研究が行なわれ、明治8(1875)年に国家主宰の勲章制度が始まります。旭日章8等が定められ、当初は賞牌、翌年には勲章と改名され、更に上級の大勲位菊花大綬章が定められました。同21年には女性を対象とした5等級の宝冠章と、旭日章上級の旭日桐花大綬章や8等級の瑞宝章、最高位の大勲位菊花章頸飾が制定されます。そして同23年には軍関係者の忠勇を表彰する金鵄勲章が創設され、29年には宝冠章が8等級に改正されました。大正8(1919)年には瑞宝章の女性叙勲が可能となり、昭和12(1937)年には単一級の文化勲章も制定されます。 しかし、昭和20年の敗戦後は、旧軍の解体や新憲法の施行と共に金鵄勲章が廃され、外国人への叙勲と文化勲章以外の生存者叙勲も停止されました。同28年には緊急を要する生存者への叙勲が再開されますが、栄典制度の法制化は叶わぬままとなります。 国家再建の功労を顕彰する必要が高まるなか、政府は同38年に閣議決定で生存者叙勲を復活させ、制度存続の危機を回避します。翌年には民主国家を反映した「叙勲基準」が閣議決定され、戦後運用の道筋が付けられました。そして平成15(2003)年、前年の閣議決定により等級廃止や種別整理を伴う新しい叙勲制度が開始され、今日に至っています。
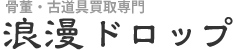






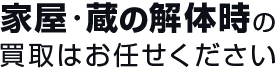
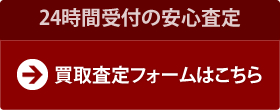
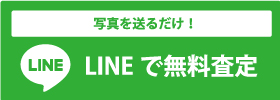

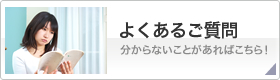





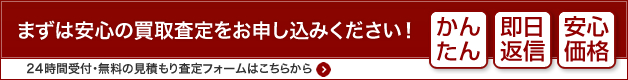

※買取商品の状態によって価格は変わりますので詳しくはお問い合わせください。