茶入の買取実績
掲載されている買取実績についてご質問などありましたら、下記までお問い合わせください。
TEL . 0120-766-299
MAIL . contact@romandrop.jp
営業時間. 9:00 ~ 18:00
ご家族が亡くなり、いざ遺品整理をしようとしても、価値が判らない、物が多すぎてどこから手をつけて良いのか判らないなど、頭を悩ますことが多いですよね。
生前大事にされていた形見の品など、無暗に手を付けるのは故人に対し申し訳ないと、処分するにもなかなか手が進まない場合もあるでしょう。
浪漫ドロップではそんな悩みの多い遺品整理を、遺品整理士の資格を持った担当者がご遺品の買取をさせて頂いています。
故人が大切にしていたコレクションや、お家の家財道具一式は勿論のこと、引き継いだ物の量が多すぎて置き場所に困っているご遺品の数々を、適切に選別させて頂き高価買取いたします。
遺品整理にて売りたい骨董品や美術品、故人が大切にしていたお品物がありましたら、浪漫ドロップへお任せください。

ご空き家やリフォーム・建て替えで古くなったお家や蔵の解体をする際、処分に困るのが解体業界で「残地物」と呼ばれる廃棄物です。
解体業者さんに処分を依頼すると追加料金がかかるので、解体費用より処理費用の方にお金がかかってしまったり、本来は売れる物でも処分費用がかかってしまったり、お客様が損してしまうケースが多いです。
そんな悩みの種の「残地物」を浪漫ドロップでは丁寧に選別・査定させて頂き価値を見出し高価買取しております。
旧家・古民家、蔵の残地物でお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
美術品や骨董品の買取は勿論のこと、格子戸や帯戸、藏戸などの建具類まで、家屋や蔵の中のお品物を無料査定・出張買取致します。
家屋や蔵を解体するご予定がありましたら、何も処分しない状態で取り壊す前にぜひ、浪漫ドロップへご連絡下さいませ。

茶道具を知る~ 茶入(ちゃいれ)~
濃茶を入れておく陶磁器製の容器
抹茶をたててお茶を入れる茶道においては、その抹茶を入れておく容器が必要になります。 茶入(ちゃいれ)は、その容器の総称です。 ただ、別のページでも説明していますが、茶入の中にはいくつか種類があり、棗(なつめ)もその1つ。 そこで茶入は、抹茶を入れる容器の中でも特に、濃いお茶を入れておく陶磁器製の容器を指すのが一般的であり、棗は木材で作られ、薄いお茶を入れてくのが原則となります。 茶席に持っていく際には象牙製の蓋でしめ、金色の糸や光沢のある豪華な絹織物で作られた袋に入れ、さらに紫檀や黒檀などの高級木材で作られた「挽家(ひきや)」と呼ばれる箱に入れ、運ばれます。
多種多様な種類がある
他の茶道具や骨董品と同じように、茶入はもともと中国から伝わったと言われています。
このような背景もあり、産地による種類分けのほか、日本における窯元のちがい、さらには、見た目の形状によるちがいなどが複雑に重なりあい、茶入の種類は無数存在。
ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。
<産地国によるちがい>
■唐物(からもの)
中国で生産された茶入の総称で、室町時代以前の作品は特に価値が高いとされています。
■和物
国焼と言います。日本で作られた茶入の総称です。
<窯元によるちがい>
瀬戸物・瀬戸焼で有名な瀬戸で作られたものが一般的であり、元祖になりますが、薩摩焼、丹波焼、高取焼なども有名で、数多くの名品を生み出しています。
<形によるちがい>
見た目の形状による種類を紹介するには、まずは茶入の全体像ならびに、どのような点をコレクターや骨董品店主が見ているのかを、説明しておきます。
高さは4~12センチメートルが一般的で、上部に抹茶を出し入れする口があり、口に向かってすぼむ下の部分を胴と呼びます。
詳しく底の方から部位を紹介すると、畳付(盆付)、糸切(底)、裾(すそ)、腰、胴、肩、甑際、甑(こしき)、捻り返し、口造、となります。
また、釉薬と土台である土の具合を、なだれ、土見、釉際などとも呼びます。
さて、見極め方ですが、まずは全体のフォルムに注意を払います。
次に、釉薬の具合。あとは、口、肩、胴、腰、糸切(いときり)の状態とバランスを見るのが一般的な査定です。
たとえば口では、肩からの捻り具合がどうか、といった点に着目します。
ここからは、形状による種類のちがいを紹介します。
■大海
金魚鉢を小さくしたような、横に広いタイプ。
大海の中でも特に小さいものは「内海(ないかい)」と呼びます。
■茄子(なすび)
言葉のとおり、野菜のなすのような形をした茶入ですが、日本のなすというよりは、米なすのようなふっくらかつどっしりとした形状が特徴です。
なお、微妙な形のちがいにより、「文琳(ぶんりん)」「尻膨(しりふくら)」などと区別されます。
もう1つ、茄子の中でも特に出来栄えが見事だと言われる「九十九髪茄子」「松本茄子」「富士茄子」の3タイプは、「天下三茄子」と称えられています。
■肩衝(かたつき)
肩の部分が横に張り出したタイプで、現在生産される茶入はこのタイプが多く見られます。
これまた茄子と同じようにトップ3の形が存在し、「初花」「楢柴肩衝」「新田肩衝」を「天下三肩衝」と呼びます。
■その他
四滴(してき)、文琳(ぶんりん)、鮟鱇(あんこう)、水指(みずさし)、手甕(てがめ)、餌畚(えふご)、飯銅(はんどう)、瓢箪(ひょうたん)、擂茶(らいざ)、樽形(そんなり)、西施(せいし)、湯桶(ゆとう)、鶴首、広口、常陸帯(ひたちおび)など。
茶入の形状はほんとうに多種多様です。
茶入には“位”がある
もう1つ、他の茶道具にも当てはまりますが、茶入には、大名物(おおめいぶつ)、中興名物(ちゅうこうめいぶつ)、名物といった具合に“位”が存在します。 位分けの方法はとてもシンプルで、ようは古いかどうかということ。利休時代の名品を「名物」とし、それ以前の年代物の茶道具は「大名物」。 逆に、江戸時代の茶人・小堀遠州時代の名品を「中興名物」と呼び、区別しています。
現代の名工も多数
焼き物の中でも茶器を得意としている窯元の作品が多く、中でも、味楽(高取焼)、加藤十右衛門(八坂窯)、三輪休雪(萩焼)、松林豊斎(朝日釜)、坂田泥華(萩焼)、上田直方(信楽焼)、などが有名です。
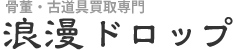
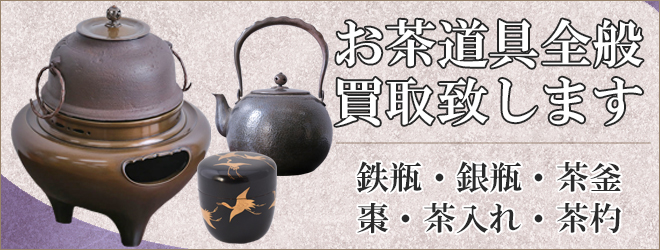


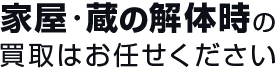
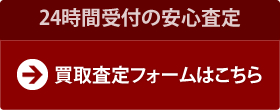
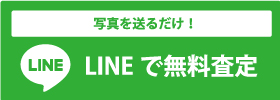

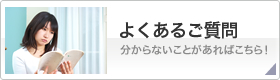





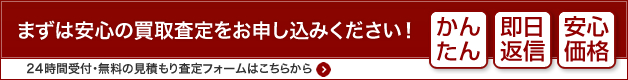

※買取商品の状態によって価格は変わりますので詳しくはお問い合わせください。